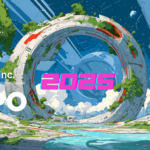カルダノ進化論:トランザクションの概念を変えるBulletという転換点

1. はじめに:いまUTxOに何が起きているのか?
私たちは今、UTxO(Unspent Transaction Output)モデルを採用するCardanoの世界で、大きな技術的転換点を迎えようとしています。
これまでアカウント抽象化(Account Abstraction)といえば、Ethereumを中心とする「アカウント型」ブロックチェーンにおける話題でした。とくにERC-4337という規格の登場により、「スマートウォレット」や「ソーシャルリカバリー(人を指定して秘密鍵を回復)」といった高度な機能が実現されつつあります。
一方で、CardanoやBitcoinのようなUTxO型ブロックチェーンは、「一つひとつの資産の入出金履歴を明確に管理できる」という構造上の強みを持つ反面、アカウント抽象化のような柔軟性を取り入れるのが難しいとされてきました。
ですが、そんな常識がいま覆されようとしています。
それが、Bulletという新しいアーキテクチャの登場です。
なぜアカウント抽象化が必要なのか?
UTxOモデルでは、ブロックチェーン上の状態(資産や情報)を「箱(UTxO)」として管理します。各トランザクションではその箱を開けて使い、新しい箱をつくることで状態を更新します。この仕組みにより、非常に強いセキュリティと予測可能な動作が得られる反面、以下のような課題がついて回りました。
• UXの複雑さ:一つの「アカウント残高」として表示されていても、実際には複数のUTxO(箱)が分散して存在するため、DApp(分散型アプリ)側やウォレット側での設計が複雑になります。
• DeFiとの相性の悪さ:たとえば、あるDEXのプールとやり取りしたいとき、他の誰かが同じUTxOを先に使ってしまうと、自分のトランザクションはエラーになります(グローバルステートの競合)。そのたびに新しい署名が必要になるという手間が発生します。
• セキュリティと柔軟性のトレードオフ:多くのCardanoウォレットでは1つの秘密鍵でアドレスが管理されています。この鍵が盗まれると、全資産が失われてしまいます。にもかかわらず、複数鍵を使ったマルチシグや「回復機能」が標準では使えないのが現状でした。
このような状況の中で、「Ethereumだけじゃない、Cardanoでも次世代のアカウント体験ができるんだ」と証明するように登場したのが、Bulletによるアカウント抽象化です。
次のセクションでは、このBulletがどのような仕組みで、トランザクションやウォレットの概念をどのように再定義するのか、詳しく見ていきます。
2. Bulletとは何か?──“署名するのは意図だけ”という発想
Bullet(バレット)は、UTxO型ブロックチェーンであるCardanoにおいて、アカウント抽象化を実現するために設計された革新的な仕組みです。
最大の特徴は、「ユーザーが署名するのはトランザクションそのものではなく、“意図(intention)”だけでいい」という考え方にあります。
◆ トランザクション署名から意図署名へ
従来のCardanoにおける取引(トランザクション)は、以下のように行われてきました:
1. ユーザーが送金やDeFi操作などの完全なトランザクションを組み立てる
2. それに対して自分の秘密鍵で署名を行う
3. ブロックチェーン上でその内容が検証・記録される
この仕組みでは、すべての入力・出力・手数料・実行タイミングが明示された完全な形のトランザクションに署名しなければなりません。
しかし現実のDeFiや分散型取引所(DEX)では、いつ約定するか分からないオーダーを出したり、状態の競合で失敗することも多く、「何度も署名し直す手間」がUXの障害となっていました。
そこでBulletはこの発想を根本から覆します。
✅ ユーザーは「やりたいこと」だけを指定し、それに署名する
たとえば以下のような「意図」だけを署名します:
• どの資産を使いたいか
• どんな条件を満たせばいいか(価格、数量、相手など)
• 最大いくらまで手数料を払ってもいいか
• 誰が署名したか(マルチシグ含む)
あとは、実際にそれを「どう実行するか」は別の役割(例えばトランザクションビルダーやシーケンサー)に任せられるというわけです。
◆ ホットキーとコールドキー:柔軟性と安全性の両立
Bulletでは、秘密鍵を次の2種類に分けて管理します:
• ホットキー(Hot Keys):日常的な利用(送金、投票、DeFi操作など)に使う鍵。署名のしやすさを重視。
• コールドキー(Cold Keys):資産管理や鍵の入れ替え、Vaultアクセスなど、より高度な操作に使う安全性重視の鍵。
この構造により、万が一ホットキーを失っても、コールドキーで回復できる設計になっています。また、マルチシグ(複数人の合意)にも柔軟に対応でき、セキュリティポリシーはユーザー側で自由にカスタマイズ可能です。
◆ Vault:DeFiのリスクから資産を守る「金庫」
Bulletは資産を「Vault(保管用UTxO)」と「流動用UTxO」に分ける概念も導入しています。
Vaultに置かれた資産は、より多くの署名やコールドキーが必要な設計にできるため、DAppのバグや悪意あるスクリプトによる資産流出から守る盾となります。
つまり、「普段使い用の財布」と「金庫」をブロックチェーン上で明確に分離できる、というわけです。
◆ アカウントモデル的UXを、UTxOの上で実現
これまでのCardanoでは、複数のUTxOを意識しなければならず、「資産残高=1つの数字」という感覚とは程遠いものでした。
しかし、Bulletは「アカウント視点」で資産を捉える設計を可能にし、より直感的でわかりやすいウォレット体験や、他のチェーンとの共通UXに近づけています。
つまりBulletとは、
✔ トランザクションの“完成形”ではなく、
✔ ユーザーの“やりたいこと=意図”に署名し、
✔ 柔軟で安全な形で実行を委ねるシステム
なのです。
この「意図ベース署名」こそが、Bulletの核であり、Cardanoにおけるアカウント抽象化の真の突破口となります。
3. DeFi体験の再定義:DEX・スワップ・シーケンサーの未来
Cardano上のDeFiはこれまで、UTxOモデル特有の制約に悩まされてきました。トランザクションの正確な構造を事前に組み、すべての入力と出力を明示し、競合が起きれば最初から作り直し——その結果、ユーザー体験(UX)は煩雑で、開発者にとっても負担が大きいものでした。
Bulletは、こうした状況を根本から変える可能性を秘めています。
「意図ベース署名」によるDeFi体験の再設計。それが、今回の革新の本質です。
◆ Orderbook型DEXの変革:「注文=署名」ではない世界
従来のCardano上のOrderbook型分散型取引所(DEX)では、次のような問題がありました:
• 注文を出すたびにトランザクションを署名し、手数料を支払う
• 注文が未約定のまま終わると、費用だけが発生してしまう
• 他の誰かが先にオーダーを処理すると、自分の注文は無効となり、再署名が必要
これらはすべて、UTxOにおける「状態の競合(グローバルステートへのアクセス制限)」によるものです。
しかし、Bulletでは注文は「意図」として署名されるため、状況は一変します:
• ユーザーはあらかじめ注文意図を署名し、ブロックチェーンに残さずオフチェーンに保存
• 実際にマッチングされたときだけ、その意図が使われてトランザクションが生成され、初めて手数料が支払われる(“pay-on-execution”)
• UTxOの競合が起きても、意図は再利用可能。再署名不要でそのまま次の機会に活かせる
結果として、DEX利用が圧倒的に軽く、柔軟になり、低コストで済むようになります。
◆ アトミックスワップの高度化:意図の合成による複数人トランザクション
アトミックスワップ(異なるユーザー・異なる資産間での同時交換)にも、Bulletは革命をもたらします。
• 複数ユーザーがそれぞれの「意図」に署名
• トランザクションビルダーがそれらを一つにまとめて実行
• いずれかの条件が満たされなければトランザクション全体が拒否され、誰の資産も動かない(All-or-Nothing実行)
さらに、フラッシュローンのような一瞬だけの借入と返済にも対応可能になります。なぜなら、意図が成功した時だけ手数料が発生し、途中で失敗しても費用はゼロだからです。
◆ シーケンサーによるスケーラブルなUX:競合からの解放
もうひとつ、UTxOで悩まされがちな「グローバルステートの競合」。
たとえば同じステーキングプールに一斉にアクセスが殺到したとき、先に送った人しか成功せず、他の人は再トランザクションを強いられる——これが従来の姿でした。
Bulletはここに「シーケンサー」という役割を導入します:
• ユーザーは意図だけを署名して提出
• シーケンサーがそれらをまとめて、最適な形でブロックに送信
• 競合はシーケンサーが解決し、ユーザーは意識せずに利用できる
• 意図に報酬を含めることで、シーケンサーへのインセンティブも明示的に設計可能
これにより、高頻度・高需要なプロトコルへのスムーズなアクセスが可能になり、UXは格段に向上します。
◆ DeFiにおける“参加と失敗”のコストがゼロに近づく
Bulletによって生まれる最大の変化は、次の一点に集約されます:
❝ブロックチェーン上で失敗しても、ユーザーは手数料を払わなくてよくなる❞
これは、UTxO型ブロックチェーンにおけるDeFi UXにおける「失敗のコスト」という重荷を根本から取り除く革命です。
より多くのユーザーが、より気軽に、より安全にDeFiに参加できる道を拓く。それが、Bulletの真の力といえるでしょう。
4. 他チェーンとの橋渡し:クロスチェーン鍵互換という展望
Cardanoは独自の技術基盤を持つため、EthereumやBitcoinといった他のチェーンから来たユーザーにとっては、馴染みのない概念や新たなウォレット操作に戸惑いを感じることが多くありました。
たとえば、Ed25519署名方式の秘密鍵を使うCardanoは、BitcoinやEthereumのSecp256k1鍵とは互換性がなく、それぞれのチェーンごとに異なる鍵ペアを管理しなければならなかったのです。
これはセキュリティ的には理にかなっていますが、ユーザー体験としては煩雑で障壁にもなり得ます。
Bulletはこの点にも果敢に切り込み、「クロスチェーン鍵互換」を実現する道筋をつけました。
◆ BitcoinやEVMと同じ鍵でCardanoを操作できる?
Bulletでは、従来のCardanoネイティブ鍵(Ed25519)に加え、
• Secp256k1(Bitcoin/Ethereumなど)
• Schnorr署名方式
といった鍵形式にも対応しています。
つまり、BitcoinやEVM系のウォレットで使っている秘密鍵を、そのままCardano上の操作に使えるようになるということです。
これは非常に画期的で、以下のようなシナリオが現実になります:
• MetaMaskで管理している秘密鍵でCardanoアカウントにアクセス
• LedgerやTrezorなどの既存ハードウェアウォレットと連携
• クロスチェーンdAppで、1つの鍵で複数チェーンを横断した署名体験を実現
◆ UTxOモデルで外部署名を使う難しさと、Bulletの工夫
UTxOモデルでは、外部で作られた署名をそのまま使おうとすると、トランザクションハッシュ自体が変わってしまい、検証が難しくなるという問題があります。
Bulletはこれに対し、次のような仕組みで解決を図っています:
1. スクリプト(スマートコントラクト)内でトランザクションの文脈(context)を取得
2. その文脈から入力・出力・手数料などを取り出してハッシュを生成
3. 生成されたハッシュに対して署名を行い、署名そのものはトランザクション本体に影響しない形で付与
この工夫により、外部鍵による署名が可能になりつつ、UTxOモデルの整合性を保てるのです。
◆ まだ実現していないが、将来が楽しみな「クロスチェーンUX」
現時点では、Bulletの鍵互換機能は「仕様と実装レベルで可能になった」という段階です。まだ具体的なウォレット統合(MetaMaskなど)やdAppレイヤーの連携は進行中ですが、基盤はすでに整っているといえます。
この仕組みが、以下のような未来を後押しするでしょう:
• クロスチェーンIDと一貫したユーザー体験
• Cardano上でBTC建てDeFiを扱うdAppの誕生
• ウォレットを切り替えることなく複数チェーンにまたがるdApp体験
Bulletは、Cardanoの外の世界と手をつなぐための“鍵の互換橋”となる可能性を秘めているのです。
5. カルダノに与えるインパクト:思想、実装、そして拡張性

Bulletは単なる新機能でも、新しいプロダクトでもありません。
それはCardanoの根底にある「UTxOモデルの思想」と「スマートコントラクトのあり方」を再構築する試みであり、今後のCardanoエコシステム全体に深い影響を与える可能性を秘めています。
✅ Bulletの開発主体とは?
Bulletの開発主体については、公式のリポジトリや論文、周辺情報から読み解く必要があります。Bulletの技術開発は「utxo-company」という開発チームによって進められており、その中心人物はIOGのKasey White氏です。IOGの公式プロジェクトというよりは、IOG所属のエンジニアが独立した形で進める実験的・先進的プロジェクトという位置づけだと思います。
✅ utxo-company とは?
現時点では「utxo-company」という組織がどの法人格や企業体に属しているかは明記されていませんが、以下の点から推測されます:
• IOGの開発者が中心人物である
• BulletはCardano専用に作られており、Aiken(TxPipe製)で記述されている
• TxPipeのDiscordにBulletの議論場所がある
これらの点を総合すると、utxo-companyはIOGと密接な関係にある開発者主導のプロジェクトグループ(もしくはIOG内の非公式開発チーム)である可能性が高いと考えられます。
また、「TxPipe」(Aikenの開発元)とも協力関係にあるようです。
このセクションでは、Bulletの登場がカルダノにもたらす3つの本質的インパクト――思想、実装、拡張性の観点から整理していきます。
◆ 1|思想:トランザクションの再定義
Bulletの最大の発明は、「トランザクションとは何か?」という問いに対して、まったく新しい答えを示したことです。
従来:
トランザクション=“すべてが完成されたもの”。その正しさをユーザーがすべて確認し、署名し、責任を負うもの。
Bullet:
トランザクション=“意図された行動を実現するための器”。その実行は他者(DAppやSequencer)と協調しながら行われ、ユーザーはその「意図」にのみ責任を持つ。
この構造によって、ブロックチェーンはより柔軟に、ユーザー中心に、そして分散的に動くようになります。
カルダノのUTxOモデルが持つ「明確な状態遷移」という強みをそのままに、「分業による実行モデル」が実現できるようになるのです。
◆ 2|実装:dAppとウォレットの新しい設計パラダイム
Bulletは既にGitHubで公開されており、Cardano上で稼働可能な形で実装済みです。これは概念にとどまらず、現実的なプロダクト開発に踏み込んでいるという点でも重要です。
とくに注目すべきは、次のようなプロジェクトとの統合が進んでいることです:
• ✅ DexHunter:Bulletによる意図ベースの注文処理を組み込んだDEX体験の構築中
• ✅ Lace(IOG公式ウォレット):意図署名に対応したUI/UXの整備を計画中
この実装が進むことで、開発者側にも次のようなメリットが生まれます:
• 複雑なトランザクション構築ロジックをアプリ側で背負わなくてよくなる
• 署名や資産管理を“意図”の形式で処理できるため、ウォレット側の設計がシンプルになる
• マルチシグ、DeFi、グローバルステート操作などの実装負荷が大幅に軽減される
今後、GovToolやCatalystなどのオンチェーンガバナンス領域への展開も視野に入ってくるでしょう。
◆ 3|拡張性:量子耐性と進化する署名スキーム
Bulletは単なる今の課題解決にとどまりません。
将来的な進化として、「量子耐性」への対応にも明言されています。
具体的には、Plutusスクリプト内で量子耐性を持つ署名方式(例:XMSSやDilithiumなど)を実行検証する仕組みの研究が進められています。これにより、
• 鍵管理の未来的脅威(量子コンピュータ)に備える
• 長期保存が必要なアカウント型ストレージやアイデンティティ管理に応用
• 公的機関や金融インフラとの統合にも適用可能
という、新たな応用領域が開けてくるでしょう。
◆ “思想 × 実装 × 拡張性”のすべてを備えたアーキテクチャ
このように、Bulletは単なるツールセットではなく、
「UTxOをもっと使いやすく、安全に、未来対応に進化させるためのアーキテクチャそのもの」と言える存在です。
• アカウント抽象化に“UTxOらしい答え”を出した
• 実装済みで現実のdAppに組み込まれ始めている
• 将来に向けた進化の余白がしっかり用意されている
この3点こそが、Bulletがエポックメイキングな存在である理由です。
6. 結び:このBulletは、ただの機能ではない。

Bulletは、単に「アカウント抽象化をCardanoでも実現できるようになりました」というだけの技術ではありません。
それは、UTxOという堅牢なモデルの上で、柔軟性・安全性・拡張性をすべて両立させた新しいブロックチェーン体験の出発点です。
◆ トランザクション体験の再構築
従来のブロックチェーンでは、トランザクションとは「ユーザーがすべてを決めて署名し、それをそのまま実行する」ものでした。
しかしBulletは、「意図を伝え、実行は他者と協調して進める」というモデルを提示しました。これは、個人の行動がネットワーク全体に調和的に影響を与える、新しいWeb3時代の実行モデルです。
• 「署名してもトランザクションが失敗していた」
• 「資産を動かすたびに不安がよぎる」
• 「複雑なスクリプトや署名が必要で、使う気になれない」
こうした従来のDeFi UXに対する不満を、Bulletは着実に解消しつつあります。
◆ コミュニティに開かれた進化と実装
Bulletのすばらしい点は、既に実装が完了しており、誰でもGitHubでコードを確認できるという**「透明性とオープン性」**です。
さらにDexHunterやLaceといった実際のdAppへの統合が進んでおり、机上の空論ではなく「動くもの」としての信頼性も確立しつつあります。
これはまさに、カルダノらしい革新のかたちです。
• 完全な形式的思考の上に立脚しながら
• 開発者コミュニティに開かれた形で
• 現実の課題を解決する実用的な実装として前進していく
Bulletは、「カルダノの強みを活かしながら、限界を乗り越える」という思想の体現そのものです。
◆ 革新は静かに、だが確実に進んでいる
Bulletは、おそらくTwitterのトレンドに乗るような派手なプロジェクトではありません。
けれども、このような技術が一歩ずつ現実に組み込まれることで、CardanoのDeFiや分散型ID、ガバナンス、社会的アプリケーションは、より堅牢で使いやすいものへと進化していきます。
革命は時に、静かな発明から始まる。
もし、Cardanoが次のフェーズへと進もうとしているとすれば、
Bulletのようなプロジェクトこそが、その扉を開く鍵になるのではないでしょうか。
🎯 この記事のまとめ:
• Bulletは、UTxO型ブロックチェーンにおけるアカウント抽象化の完成形
• ユーザーは「意図」だけを署名し、実行はネットワークに委ねられる
• DeFiやマルチシグ、Vault、シーケンサーなどによりUXとセキュリティが両立
• 他チェーンとの鍵互換により、クロスチェーンなWeb3体験の土台を提供
• 実装済みかつオープンソースで、現実のdAppとの統合も進行中
もしこの記事が気に入っていただけましたら、SIPO、SIPO2、SIPO3への委任をどうぞよろしくお願いいたします!10ADA以上の少量からでもステーキングが可能です。
シリーズ連載:進化するカルダノ・ベーシック
エポックな日々
ダイダロスマニュアル
ヨロイウォレット Chromeブラウザ機能拡張版マニュアル
Laceマニュアル
SIPOはDRepへの登録と活動もしております。もしSIPOの活動に興味がある方、DRepへの委任方法について知りたい方は以下の記事をご覧ください。また委任もぜひお願いいたします。
SIPOのDRepとしての目標と活動方針・投票方法
SIPOのDRep投票履歴:https://sipo.tokyo/?cat=307
ダイダロスの方は最新バージョン7.0.2で委任が可能になりました。
SIPOのDRep活動にご興味がある方は委任をご検討いただければ幸いです。
DRep ID:
drep1yffld2866p00cyg3ejjdewtvazgah7jjgk0s9m7m5ytmmdq33v3zh
ダイダロス用👇
drep120m237kstm7pzywv5nwtjm8gj8dl55j9nupwlkapz77mgv7zu7l
二つのIDはダイダロス以外のウォレットではどちらも有効です。ADAホルダーがSIPOにガバナンス権を委任する際に使用できます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。