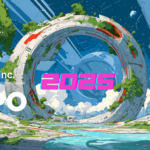選べる通貨、分かち合う価値、再起する起業家たち──Money20/20から見える次世代経済のリアル

序章:アムステルダムから始まる次世代金融の黙示録──Money 20/20 Europeとは何か
2025年6月、オランダ・アムステルダムにて開催された「Money 20/20 Europe」は、世界中のフィンテック業界関係者が集結する、ヨーロッパ最大級の金融テクノロジーイベントとして注目を集めました。会場となったRAIアムステルダムには、3日間で2,000社を超える企業、100カ国以上からの来場者、340名以上の業界リーダーたちが集まり、次世代の金融システムについて議論を交わしました。
このイベントの大きな特徴は、単なる最新技術の展示にとどまらず、社会課題や制度設計を含めた「金融の本質的な再構築」に焦点が置かれている点にあります。2025年の開催テーマは「分散型金融(DeFi)と伝統的金融(TradFi)の統合」、そして「プライバシーとアイデンティティの未来」でした。これは、ただのトレンドではなく、今後の経済基盤そのものを左右する鍵として位置づけられていたのです。
中でも象徴的だったのが、カルダノ創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏の一連の講演でした。彼は複数のセッションに登壇し、「第四世代の暗号通貨」「トークノミクスによる協調経済」「プログラマブルなプライバシー」など、現在進行形で構築されつつある分散型経済の未来像について語りました。彼のスピーチは、単なるプロジェクト紹介ではなく、暗号資産が持つ文明論的な可能性を提示するものであり、多くの聴衆に強い印象を与えていました。
Money 20/20 Europeは、これまでの金融業界の常識が通用しない未来が、すでに始まっていることを可視化する舞台となりました。DeFiとTradFiが対立する概念ではなく、融合しながら共通の「FI(Finance)」へと向かっていくプロセス──そこには、通貨の自由、価値の選択、そして挑戦者たちにとっての「再起のチャンス」という、新たな経済のリアルが広がっています。
第1章:分断から統合へ──「FI」だけが残る時代の金融観
2025年、暗号資産と伝統的金融はもはや別々の世界ではありません。Money 20/20 Europeの壇上でチャールズ・ホスキンソン氏が語った「TradFiとDeFiを超えて、ただの“Finance(FI)”になる時代が来る」という言葉は、金融界における新たな認識の始まりを象徴しています。
ホスキンソン氏は、「暗号資産はもはや“代替手段(alternative rail)”ではなく、伝統的な金融インフラと融合しつつある“統合手段(merge rail)”だ」と明言しました。これは、ブロックチェーン技術が「外部の異物」として警戒されていた時代を越え、今や既存のシステムの中に組み込まれる存在になりつつあるという現状を的確に表しています。
暗号資産と伝統金融を分けて論じる時代は、すでに終わりを迎えようとしています。金融の機能──価値の保存、移転、証明、交換──は、ブロックチェーンというレールの上で、より迅速かつ柔軟に提供され始めています。これにより、国家や地域、企業ごとの垣根を超え、個々のユーザーが自らの財務基盤を構築・運用する自由が拡がっているのです。
しかし、この「統合」には課題も伴います。規制やKYC(本人確認)、AML(マネーロンダリング対策)といった既存の制度と、パーミッションレスで自由なブロックチェーンとの間には、依然として制度的・技術的な「摩擦(friction)」が残っています。ホスキンソン氏は、この摩擦の本質は「プライバシー」だと語ります。つまり、公開性を前提としたブロックチェーンが、いかにして選択的な開示やアイデンティティ管理を実現し、従来型金融のルールと接続するかが次のステージなのです。
このような「融合のための制度設計」を進めることは、単に暗号資産を合法化するという意味を超えています。それはむしろ、既存の金融システムが抱えていた不平等や不透明さ、非効率性といった問題を是正するための“リビルド(再構築)”のチャンスであると、ホスキンソン氏は主張します。
かつて分断されていた「TradFi」と「DeFi」は、もはや競合する存在ではなく、相互補完しながら新たな共通基盤「FI(Finance)」へと収束しつつあります。この構造的変化こそが、今後10年の金融を根本から塗り替えていくことでしょう。
次章では、この金融統合の基盤となる「トークノミクス(トークン経済)」が、どのようにして500万人規模のネットワークを生み出し、分散型経済の動員力となったのかを掘り下げてまいります。
第2章:15年で5億人──トークノミクスが可能にした”非中央集権的動員力”
2025年現在、暗号資産業界はおよそ5億人以上のユーザーを抱え、発行された暗号資産の数は1,400万種類を超えるとされています。この驚異的な成長の背景には、従来の企業組織やマーケティングとは異なる、新たな「動員力のメカニズム」が存在します。それが、チャールズ・ホスキンソン氏が「この業界の真のスーパーパワー(超能力)」と表現するトークノミクス(Tokenomics)です。
ホスキンソン氏は、Money 20/20の講演で次のように語っています。
「私たちは中央組織も調整機関もなく、ただひとつのインセンティブ関数だけで、ゼロから5億人のネットワークを作り出しました。これは、あらゆる金融機関が注目すべき力です。」
トークノミクスとは、単なる「トークンを使った報酬設計」ではありません。それは、ネットワークに参加する個人が、経済的インセンティブを通じて自発的に行動し、他者を巻き込み、エコシステムを拡大するという全く新しい協調モデルです。中央からの命令やプロモーションがなくても、ユーザー自身がプロジェクトの伝道者となり、トークン価値の向上とともに利害が一致する。この“自走する経済”の力こそが、伝統的なビジネスモデルにはなかったダイナミズムを生み出しています。
このような構造は、単なる理論ではなく実際に機能しています。CardanoやEthereumのようなレイヤー1プロジェクトはもちろん、DeFi、NFT、DAOといった新領域でも、プロトコルのユーザーが同時にその成長の担い手であり、株主であり、共同意思決定者として振る舞うエコシステムが生まれています。
特に注目すべきは、この動員力がトップダウンではなくボトムアップで機能している点です。これは、国家や企業といった中央集権的な意思決定構造とは異なり、より有機的かつレジリエントな形で社会基盤を構築する可能性を示しています。
さらに、トークノミクスにプライバシーと選択的開示の仕組みが組み込まれたとき、暗号資産は伝統金融との接続性を大きく高めることになります。ホスキンソン氏は、「これにより、規制されたビジネスや、既存の業界プレイヤーが安心して参加できる“橋”が生まれる」と述べています。
つまり、トークノミクスとは単なるマーケティング手法や報酬設計ではなく、「分散型協調経済」の中核技術であり、民主化された経済参加の手段であるということです。そこには、かつてシリコンバレーが独占していた“起業家精神”を、世界中の誰もが持てるようになる──そんな未来への扉が開かれています。
次章では、この分散型経済の推進に不可欠な要素である「プライバシー」と「アイデンティティ」の関係、そして“第四世代”に求められる要件について掘り下げてまいります。
第3章:第四世代の要件──ID×プライバシー×選択可能な通貨経済

チャールズ・ホスキンソン氏がMoney 20/20 Europeで繰り返し強調したキーワードのひとつが「第四世代の暗号通貨」です。これは、ビットコインのような「価値の移転」(第一世代)、イーサリアムがもたらした「プログラム可能な価値」(第二世代)、そしてCardanoなどによって拡張された「スケーラビリティ・相互運用性・ガバナンス」(第三世代)を土台としながら、ID(アイデンティティ)とプライバシーの両立を前提とする、次の時代の設計図を意味しています。
プライバシーは「選択的な開示」でなければならない
ブロックチェーンは透明性と公開性を前提とした技術です。ところが、現実のビジネスや社会活動には、「見せたくない情報」も数多く存在します。ホスキンソン氏は、これを「公開性と機密性の緊張関係」と呼び、それを解決する手段として「プログラマブル・プライバシー」の重要性を説いています。
その核にあるのが、ゼロ知識証明や選択的開示といった技術です。たとえば、米国のバーでお酒を注文する際、年齢確認のために身分証を提示しますが、実際に必要なのは「21歳以上か否か」というYes/Noの情報だけです。それにもかかわらず、住所、氏名、顔写真といった個人情報まで晒してしまっているのが現実です。ホスキンソン氏はこうした「過剰開示」の常態化を問題視し、「必要な情報だけを、必要な相手に、必要な範囲で開示できる」仕組みの構築こそが第四世代に求められる要件であると主張します。
アイデンティティの主権を取り戻す
このプライバシー設計と表裏一体で語られるのが、分散型ID(DID:Decentralized Identifier)の概念です。これまで、個人のアイデンティティ情報は政府や銀行、SNS企業などの“中央機関”に預けられ、個人はその利用を許可するだけの立場に甘んじてきました。
しかし第四世代の設計思想では、IDそのものが「本人のもの」であり、本人が自分の意思で開示・証明・共有をコントロールできる仕組みが重視されます。これは「自己主権型アイデンティティ(SSI)」とも呼ばれ、W3C(World Wide Web Consortium)でも標準化が進められている国際的な潮流です。
通貨は「選べるもの」になる
さらに、ホスキンソン氏は将来の金融像として、「一人ひとりが“自分だけの財布”を持ち、どの通貨で支払うかを選択し、相手が望む通貨で受け取れる」世界を描いています。
それはドルやユーロだけでなく、ビットコインやADA、金や銀、不動産トークン、労働クレジット、NFT、そしてロイヤリティポイントやIP権利など、あらゆる価値がトークン化され、選択肢となる社会です。そして、それを支えるのが「ID」と「プライバシー」という2つの土台であり、両者が揃うことで、ユーザーは本当に「自分の財布」を持つことができるのです。
第四世代とは、単なる技術の進化ではなく、「選べる」「隠せる」「証明できる」──この三拍子がそろった経済空間の実現を目指すものです。
このような条件を満たすことで、初めて分散型経済は既存の制度や大手企業とも対話できるようになります。そしてその先にあるのは、誰もが自身の価値と信用を「自分で使いこなす」ことのできる真の経済的主権の時代です。
次章では、このような構想がなぜ「再起のチャンス」となるのか──Web3がもたらす起業家精神の再燃について掘り下げてまいります。
第4章:一人ひとりの再起のチャンス──Web3がもたらす“Second Chance”
Money 20/20 Europeの講演で、チャールズ・ホスキンソン氏は暗号資産とWeb3の本質を語る中で、印象的な言葉を繰り返しました。それは、「この業界は、私たち全員に“Second Chance(再起のチャンス)”を与えてくれる」というメッセージです。
金融システムにおける“格差の固定化”
私たちが日常的に使っている既存の金融システムは、一見便利で安全に見えますが、実際には不透明な手続きや特権的なアクセス制限、グローバルな不平等を内包しています。国境をまたいで送金しようとすれば、知らない誰かに止められる。ビジネスを立ち上げようとしても、規制や既得権益の壁に阻まれる。ホスキンソン氏はこうした現実を、「多くの人が、見えない“信用の壁”に閉じ込められている」と表現しました。
このような構造の中では、新しいアイデアや小さな挑戦が正当に評価されることは難しく、結果として機会の格差は世代を超えて再生産されてしまいます。とりわけ、起業家精神を持つ人々にとって、この状況は“夢を諦めさせる装置”として機能してきたと言えるでしょう。
Web3は「信用の起点」を個人の手に戻す
それに対し、Web3の世界はまったく異なるロジックで動いています。分散型台帳上では、誰もが平等にアクセスでき、コードとスマートコントラクトがルールを定義します。何を知っているか、どんな履歴を持っているか、どの国に住んでいるかではなく、何を実行したか、どんな価値を創出したかが正当に記録され、可視化されるのです。
そして、そこには仲介者も、不透明な審査基準もありません。誰かに許可を得ることなく、プロジェクトを立ち上げ、価値をトークン化し、世界中のユーザーとつながることができます。まさにこれは、**「もう一度、ゼロからやり直すための公平な舞台」**であり、あらゆる人々に再起の機会を提供する経済モデルだと言えるでしょう。
挫折した起業家も、規制に潰されたアイデアも、再び立ち上がれる
ホスキンソン氏は講演の中で、「あなたたちは、自分のキャリアで数え切れないほどの“理不尽”を経験してきたはずだ」と聴衆に語りかけました。コンプライアンスチームとの対立、取引拒否、不合理な書類要求、新規事業の却下……。伝統的な金融の世界では、情熱と実力だけではどうにもならないことが多々あるのです。
しかし、Web3はその枠組みを変えます。それまで“無理”とされていたアイデアが実現可能になる世界が、技術的に、そして制度的に少しずつ整備されてきています。現に、分散型金融(DeFi)やNFT、DAOといった新たな経済圏では、これまでにない発想のプロジェクトが立ち上がり、世界中のユーザーや開発者が支援しています。
このような環境は、単に技術者や金融関係者にとっての話にとどまりません。小さなビジネスを営む人、アーティスト、地域のコミュニティリーダーなど、あらゆる「挑戦者」にとっての再起の舞台が整いつつあるのです。
「なぜ、15年経ってもこの業界にいるのか」
最後にホスキンソン氏は、自身がなぜこの業界に15年も関わり続けているのかという問いに答えました。
「それは、この業界が、私たち全員にもう一度夢を見ることを許してくれるからです。」
この言葉には、技術でも経済でもない、“人間の可能性”への信頼が込められています。Web3が切り拓く未来とは、かつて挫折した誰もが再び立ち上がり、新たな価値を生み出せる世界。その核心には、経済のルールを変えることではなく、「誰にでもやり直す自由がある」ことを制度として保証する思想があります。
次章では、この自由と選択の世界において、「ウォレット=あなたの経済主権」がどのように社会と接続し、通貨・価値の選択肢を可能にするのかを探ってまいります。
第5章:“トークン+選択”が創る新しい決済世界──あなたのウォレットが世界をつなぐ

かつて通貨とは、国家が発行し、国民がそれに従うものでした。しかし今や、通貨は「選ぶもの」へと変わりつつあります。Money 20/20 Europeでチャールズ・ホスキンソン氏が描いた未来とは、まさにその常識を根底から覆すものでした。
彼が語ったのは、「自分のウォレットの中に、ドルやADA、ビットコインだけでなく、金や不動産、ロイヤリティポイント、労働クレジット、知的財産トークンまでを自由に保有できる世界」、そして「支払うときには自分が支払いたいトークンで支払い、相手は受け取りたいトークンで受け取る」という双方向選択の経済社会です。
ウォレットは“あなたの経済的自己”になる
この構想において、ウォレットは単なる支払い手段ではありません。それは、あなたがどの価値を重視し、どの経済圏に属し、何に信用を置いているかを反映する“経済的アイデンティティ”の集約体です。
ドルを持つか、ビットコインを持つか。地元商店のポイントを重視するか、グローバルな金地金トークンを保有するか。そうした選択が、政治や宗教と同じように「個人の意思と信念」を体現する時代が、すぐそこまで来ています。
そして重要なのは、それらを自由に組み合わせ、運用できる“構成力”がユーザーに与えられている点です。伝統的な金融では、銀行口座と証券口座とポイントカードとNFTウォレットは全く別物として扱われます。しかし分散型の仕組みでは、それらが一つのウォレットに統合され、APIやスマートコントラクトによってシームレスに機能するのです。
支払う自由と、受け取る自由
この「選択可能な価値のやり取り」は、単なる理想論ではありません。実際にCardanoや他のブロックチェーンプロジェクトでは、マルチアセット機能やBabel Fee、Atomic Swapのような仕組みにより、複数トークン間の相互運用が現実のものとなりつつあります。
ホスキンソン氏は、「自分が支払いたいもので支払い、相手が望む形で受け取れる取引こそが、真にパーミッションレスでグローバルな商取引を可能にする」と強調します。これは言い換えれば、「価値観の多様性を認め合う経済」の誕生でもあります。
国家、企業、地域、文化の違いを超え、“通貨という言語”を翻訳し合うネットワークができれば、国際貿易も地域通貨も、個人間の価値交換も、ひとつの土台の上で成り立つことになります。
選択の裏に必要な“信頼の設計”
もちろん、こうした経済の前提には「信頼」が必要です。誰がトークンを発行し、誰がその価値を担保し、どのような条件で交換が成立するのか。そのすべてをスマートコントラクトと分散型ID、そして選択的プライバシーで定義する必要があります。
ホスキンソン氏はこの信頼の設計こそ、IOG(Input Output Global)が取り組んでいる最重要テーマであると述べます。ウォレットの中に何が入り、どのように動き、誰と接続されるか──その全てを支えるプロトコル設計が、今まさに進化しているのです。
第6章:IOGの役割──私たちは道具をつくる者である
チャールズ・ホスキンソン氏が創設したInput Output Global(IOG)は、単なるブロックチェーン企業ではありません。同社は、Cardanoをはじめとする分散型インフラの開発を通じて、「分散型社会の設計図」を実装することを使命としています。そしてホスキンソン氏自身は、Money 20/20 Europeで繰り返しこう述べていました。
「私たちはプロダクトセールスではなく、“道具をつくる者(Tool Builders)”です。」
この言葉には、IOGの活動の根底にある哲学がにじんでいます。IOGはユーザーに対して完成された製品を提供するのではなく、誰もが自分自身の経済、社会、組織を構築するための“レゴブロック”のようなツール群を設計・提供しているのです。
ツールとしての「プロトコル設計」
そのツールの代表例が、Cardanoに搭載されている様々なプロトコル群です。ステーキング、スマートコントラクト、ガバナンス、マルチアセット、Babel Fees、Hydra(L2)、そしてPlutusとMarloweといった金融向けDSL(ドメイン固有言語)──これらすべてが、単なる「使われる機能」ではなく、「誰かが何かを作るための基礎部品」として設計されています。
このような設計思想は、OSS(オープンソースソフトウェア)の文脈と重なります。特定企業に閉じられたAPIではなく、誰もがアクセスでき、改良でき、参加できる公共インフラとしてのプロトコル群。その土台を構築しているのがIOGの役割です。
“協調を生み出す設計”という挑戦
ホスキンソン氏は「暗号資産業界の本当の力は、トークノミクスによって人々を協調させる力にある」と語ります。この協調の仕組み──つまり経済的インセンティブ、ガバナンス構造、プライバシー制御、ID管理の在り方などをどう設計するかこそが、IOGの技術的チャレンジの中心にあります。
IOGの取り組みは、「どのブロックチェーンが速いか・安いか」ではなく、「どのプロトコルが最も多様で公正な協調行動を引き出すか」という視点で進められているのです。これは、金融のみならず、教育、医療、土地登記、投票など、あらゆる分野に通じる設計思想でもあります。
道具を通じて、“選ばれる未来”を設計する
道具とは、それを手にした人によって未来のかたちが変わるものです。IOGが目指すのは、特定のイデオロギーを押し付けることではなく、「選べる未来」を広げることです。
誰もが自分の経済を設計でき、コミュニティのガバナンスに参加でき、トークンを通じて他者と信頼を築ける。そうした“選ばれる未来”の実現を、IOGはツールを通してサポートしているのです。
このようにして構築された分散型社会の土台は、IOG自身が統治するのではなく、ユーザーや開発者、起業家たちによって自律的に発展していきます。その意味でIOGは、未来のインフラを設計する「設計者」であると同時に、利用者に力を委ねる「裏方」でもあります。
第7章:生成AIと比較される協調性──Cardanoが挑む“APIによる競争”
2025年現在、生成AI(Generative AI)は飛躍的な進化を遂げ、ビジネスや社会に広く浸透しつつあります。ChatGPTをはじめとするAIツールは、既存の業務効率を劇的に改善し、個人の創造力を拡張する存在として位置付けられています。けれども、その背後には一貫した「中央集権的制御」と「閉じたAPIエコシステム」という性質も見え隠れします。
それに対して、チャールズ・ホスキンソン氏はMoney 20/20 Europeの講演において、「トークノミクスを基盤としたブロックチェーンは、別の意味での“人間の集合的創造力”を引き出す協調インフラである」と語りました。つまり、生成AIが“個人の出力”を加速するものであるならば、ブロックチェーン、特にCardanoのような設計思想を持つプロジェクトは、“集団の協調的意思決定”を拡張するプラットフォームであるという位置付けです。
中央集権AI vs 協調型プロトコルの競争軸
今日のAIは、高性能なモデルとデータ資源を持つ一部の巨大企業(いわゆるマグニフィセント7)によってコントロールされています。そのモデルやAPIは、ライセンスによって制限され、アルゴリズムの中身はブラックボックスのままです。つまり、その出力結果を信じるしかない構造になっています。
一方で、Cardanoのような分散型プロトコルは、「誰がどう計算し、どうガバナンスに参加し、どんなトークン設計でインセンティブが動いているのか」がすべてオープンで検証可能です。そして、個人がプロトコルに対してコードや提案を提出し、ステークホルダー全体の合意形成によって機能が進化していきます。
この構造は、ある意味で「オープンソースAI」へのアンチテーゼでもあり、「協調によって社会を拡張する」という異なる文明モデルを体現していると言えるでしょう。
APIによる競争と相互運用性の本質
ホスキンソン氏は、GoogleがGPTに800万人のユーザーを一気に接続できた背景に「既存のネットワーク効果」があると語っています。しかしそれと同時に、Cardanoのようなブロックチェーンが本当に競争できる道は、「APIによって相手のエコシステムに“共存”できること」にあると述べました。
つまり、Cardanoが他のブロックチェーンやWeb2企業と張り合うのではなく、相手のサービスやトークンと接続し、協調しながら価値を拡張する設計を持つことが本当の競争優位となるという考え方です。
この「APIによる競争」とは、物理的な速度や処理能力ではなく、どれだけ多様な参加者が相互接続でき、協調的にエコシステムを拡張できるかという視点での戦いです。Cardanoが重視しているのは、まさにこの接続性と可読性、そして“参加することで強くなる経済”という設計なのです。
トークノミクスが生む「自律分散的な成長曲線」
Cardanoのエコシステムでは、DApps開発者やSPO(ステークプールオペレーター)、DRep(ガバナンス代表者)、利用者、研究者が、それぞれの立場でネットワークの成長に貢献しています。しかも、これらの活動はすべてトークンインセンティブとガバナンスによって調整されており、外部からの広告や資金に依存せずとも成長できる自律分散的な成長曲線を描くことが可能です。
この構造は、広告予算やサーバー性能ではなく、「コミュニティの意志と貢献度」が競争力を生むという、全く異なるゲームのルールを提示しています。
つまり、生成AIが一方向の出力を拡張する「個別知能の文明」であるならば、Cardanoが示す方向性は「相互接続・共同設計による社会的知能の文明」です。そしてその勝負の舞台は、スピードやシェアではなく、いかにオープンに協調可能なプロトコルを築けるかという「APIによる競争」にあるのです。
次章では、この協調型社会の構造的基盤を築く上で避けて通れない、“暗号資産史の進化”を振り返りながら、Cardanoがどのようにこの第四世代の未来を準備してきたのかを探ってまいります。
第8章:進化の系譜──第一〜第四世代までの暗号資産史を振り返る
Money 20/20 Europeにおけるチャールズ・ホスキンソン氏の講演は、単なる未来志向のビジョンだけでなく、過去15年間の暗号資産の進化の“地層”を丁寧に辿るものでした。そこには、中央集権に代わる新しいインフラの誕生と、その進化の必然性が刻まれています。
この章では、ホスキンソン氏の語った四つの世代のフレームワークをもとに、暗号資産の技術的・制度的な進化の流れを振り返ります。
第一世代:価値を動かす──ビットコインの誕生
2009年、ビットコインが登場したとき、金融の世界に走った衝撃は大きなものでした。それまで30年以上にわたり、暗号学者たちが「電子メールのように金銭を送る方法」を模索してきた中で、ついに「中間業者を必要とせず、価値をインターネット上で直接送信できる」仕組みが実現したのです。
この第一世代は、主に「分散型の価値移転手段」としての機能に特化していました。単一のユースケース、単純な送金機能、プログラマビリティの欠如──それでも、それは人類にとって初の“金融のパーミッションレス化”であり、非常に大きな一歩でした。
第二世代:価値にロジックを載せる──スマートコントラクトの登場
その後、イーサリアムを代表とする第二世代が登場し、ブロックチェーンに「プログラム可能な価値」を導入しました。スマートコントラクトにより、トークンの発行、分散型取引所、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)などが可能になり、応用の幅が一気に拡がりました。
ただし、スケーラビリティの課題、手数料の高騰、ネットワークの分断、ガバナンスの不在といった問題も明らかになり、次なる進化が求められるようになります。
第三世代:スケーラビリティとガバナンス──Cardanoの挑戦
Cardanoは、これらの課題に正面から向き合うプロジェクトとして生まれました。第三世代では以下の3つが大きなテーマとなります。
- スケーラビリティ:世界中の人々が同時に利用しても耐えうる性能
- 相互運用性:異なるチェーンや金融機関との接続性
- ガバナンス:アップグレードや方針決定のプロセスをオンチェーンで実現する仕組み
ホスキンソン氏は、「ビットコインには手紙を送る機能しかなかったが、第三世代には“メールアプリ”が必要だ」と述べました。つまり、多様なニーズを内包しながら、持続可能な社会インフラとして進化するための構造改革が第三世代の中心テーマだったのです。
Cardanoではこれを、形式手法に基づく安全性の追求、ステークベースのコンセンサスメカニズム(Ouroboros)、CatalystやVoltaireといったオンチェーンガバナンスで具体化しています。
第四世代:自己主権と選択可能性──統合の時代へ
そして現在、私たちは第四世代に足を踏み入れています。この世代では、過去の全ての要素──価値の移転、プログラマビリティ、スケーラビリティ、ガバナンス──を統合しながら、さらに「選べる通貨」「自己主権型ID」「プライバシーと選択的開示」といった新たなレイヤーを加えています。
第四世代とは、単なるテクノロジーの高度化ではなく、「個人が自らの経済的環境を選び取ることができる世界」の構築を目指す運動です。そこには、トークンの多様性だけでなく、社会制度との接続性、規制当局との対話、そして地球規模の協調可能性といった課題と可能性が共存しています。
ホスキンソン氏が語ったように、「この第四世代は、すべての人が平等に参加でき、自己決定権を持ち、かつ持続可能な社会経済システムを自ら構築できるインフラ」の実現に他なりません。
こうして見てくると、暗号資産の歴史とは、単に通貨が進化してきたのではなく、人類の経済的主権と協調の可能性をめぐる物語だったと言えるかもしれません。
最終章では、この四世代の集大成とも言える「ただのFinance(FI)」という概念に立ち戻り、なぜ今Cardanoがその未来像の中心にいるのかをまとめていきます。
最終章:FIという未来──通貨・制度・文明を“選べる”時代へ
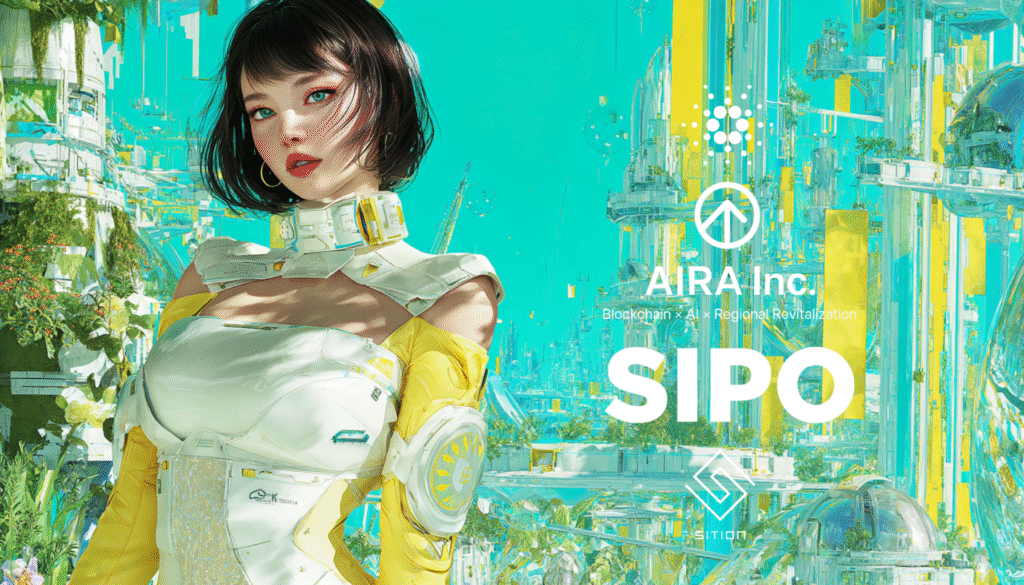
暗号資産がもたらした技術革新は、単なる金融商品や投資対象の話にとどまりません。それはむしろ、「通貨とは何か」「国家とは何か」「制度とは誰のためにあるのか」という根本的な問いを、私たちに投げかけています。
チャールズ・ホスキンソン氏がMoney 20/20 Europeの講演で繰り返し語ったのは、この15年にわたる進化の果てに、私たちは「ただのFinance(FI)」という新しい地平に到達しつつあるということです。DeFiでもTradFiでもなく、「FI=Finance」という共通の土台。そこでは、個人、企業、国家、そしてAIまでもが、共通のルールと技術基盤の上で相互作用を持つことになります。
この“ただのFI”というビジョンは、分断の時代を終わらせ、接続と選択の時代を切り拓こうとするものです。
通貨を選ぶ自由、制度を選ぶ自由
これまで通貨は、国家に紐づくものでした。生まれた場所、住んでいる国によって、使える通貨や利用可能な金融サービスが制限される──それが当たり前の世界でした。しかし今や、デジタルウォレットの中に、ビットコイン、ADA、USDC、金、NFT、さらには地域トークンやポイントが共存できる時代が来ています。
これは単なる“複数通貨対応”ではありません。それぞれの通貨が持つ思想や設計(インフレ型/デフレ型、管理型/自律型など)を選び、自分の経済的価値観に合った通貨を使う自由が保障されるということです。
さらに、この自由は制度やガバナンスにも広がります。DAOやDRep、自己主権型IDによって、自らが属する経済圏のルールやガバナンスに参加し、自らの意志で「制度そのもの」を選び取ることが可能になるのです。
インフラではなく「文明」を設計するという発想
第四世代のブロックチェーン、特にCardanoが目指しているのは、金融システムの刷新を超えて、文明のOSを設計するという挑戦です。
この“文明OS”では、以下のような原則が基盤になります:
- 信頼はアルゴリズムとオープン性によって担保される
- ガバナンスは参加によって構成される
- 通貨は選択肢であり、手段である
- プライバシーはデフォルトであり、開示は選択的である
- 経済参加はグローバルであり、誰にも制限されない
これは、中央が定めたルールに従う時代から、一人ひとりが自らの文明設計に関与する時代への転換を意味します。
「再起」と「再設計」を同時に与える金融へ
このような未来は、特権層だけのものではありません。起業に失敗した人、信用情報を持たない人、国境で排除されてきた人々にとって、Web3やCardanoが提供するツールは、「再起の機会(Second Chance)」であり、かつ「自分自身の社会を再設計するための道具箱」でもあります。
ホスキンソン氏は、次のように締めくくりました。
「この業界が与えてくれる最大の贈り物は、“選ぶ自由”です。
どの通貨を使うか、どの経済に属するか、どんな価値観で生きるか。
私たちは今、そのすべてを自分で選べる時代を創りつつあるのです。」
結びにかえて
本稿で紹介したMoney 20/20 Europeでの一連の講演は、Cardanoの技術的進化やガバナンス構想を超えて、新たな経済文明の設計書とも言えるものでした。
それは、選べる通貨。
分かち合える価値。
そして、再起する起業家たち。
この三つの要素が揃ったとき、世界は新しいかたちの金融と社会へと進化します。Cardano、そしてIOGが提示するのは、まさにその「再設計可能な未来」です。
次のページを開くのは、私たち自身です。
補足特集:Midnightが担う“第四世代”の実装基盤──語られなかった主役

今回のMoney 20/20 Europeにおいて、チャールズ・ホスキンソン氏は「Midnight(ミッドナイト)」というプロジェクト名を一度も口にしていません。しかし、その講演の内容を注意深く追えば、プライバシー、選択的開示、自己主権型ID、協調型ガバナンスなど──Midnightがまさに実装しようとしている機能や思想が随所に現れていたことは明白です。
ホスキンソン氏が語った「第四世代のブロックチェーン」とは、単にスケーラブルでガバナブルなプロトコルにとどまらず、「プライベートとパブリックを共存させた社会的インフラ」そのものです。そして、それを最も直接的に体現しているのがCardanoのパートナー(サイド)チェーン構想に基づく『Midnight』です。
Midnightとは何か?
Midnightは、IOG(Input Output Global)が開発を進めるデータ保護重視型のサイドチェーンであり、次のような特徴を備えています:
- ゼロ知識証明(ZKP)を活用した、プログラマブル・プライバシーの実現
- 自己主権型アイデンティティ(DID)との統合によるアクセス制御と開示管理
- GDPRやHIPAA等の規制要件に準拠した、オンチェーン・コンプライアンスの土台
- 企業や公共機関が安心して使える、選択的な可視性を持つスマートコントラクト
つまりMidnightは、「透明性」を前提とする従来のブロックチェーンとは対照的に、「守ることを前提とした公共インフラ」として設計されているのです。
なぜ講演では語られなかったのか?
Midnightが直接的に言及されなかった理由は、おそらく「プロダクト名よりも原理・思想への共感を促す戦略」のような事情があると考えられます。
実際、ホスキンソン氏の講演ではMidnightという名前こそ登場しませんでしたが、その機能的中核──「プライバシーはデフォルト、開示は選択的」「IDと財の制御権を個人に戻す」──というテーマは繰り返し登場しており、それこそがMidnightの存在意義と深く結びついています。
Cardano × Midnightが描く“FI”の完全体
本記事のテーマである「FI(Finance)」の再定義とは、分散性・選択性・協調性を備えたインフラの実装によって初めて成し遂げられます。そして、その構造を担うのがレイヤー1としてのCardanoであり、そのセキュリティや規模拡張の“影の支柱”として動くのがMidnightなのです。
Midnightが本格的に稼働することで、以下のような未来が現実になります:
| 領域 | 可能になること |
|---|---|
| 個人 | プライベートなトランザクションと自己主権型IDの統合 |
| 企業 | 規制遵守型のDApps運用(内部監査・KYC・AML) |
| 社会 | 公共サービスのブロックチェーン化とデータ保護 |
| Cardano全体 | プライバシー重視のユースケース追加によるエコシステム拡張 |
Midnightは単なる“匿名取引チェーン”ではなく次世代社会の設計基盤となる「法とプライバシーを両立させた分散型公共圏」として設計されています。
あらためて──語られざるMidnightに耳を傾ける
今回のMoney 20/20 Europeでは、Midnightという言葉が語られることはありませんでした。しかし、語られなかったからこそ、そこには意図と戦略があり、Midnightこそが「選べる通貨、分かち合う価値、再起する起業家たち」の実装基盤であるという事実は変わりません。
Cardanoが示した“第四世代”のビジョン。
その静かなエンジンとして、Midnightは確かに動き始めています。
もしこの記事が気に入っていただけましたら、SIPO、SIPO2、SIPO3への委任をどうぞよろしくお願いいたします!10ADA以上の少量からでもステーキングが可能です。
シリーズ連載:進化するカルダノ・ベーシック
エポックな日々
ダイダロスマニュアル
ヨロイウォレット Chromeブラウザ機能拡張版マニュアル
Laceマニュアル
SIPOはDRepへの登録と活動もしております。もしSIPOの活動に興味がある方、DRepへの委任方法について知りたい方は以下の記事をご覧ください。また委任もぜひお願いいたします。
SIPOのDRepとしての目標と活動方針・投票方法
SIPOのDRep投票履歴:https://sipo.tokyo/?cat=307
ダイダロスの方は最新バージョン7.0.2で委任が可能になりました。
SIPOのDRep活動にご興味がある方は委任をご検討いただければ幸いです。
DRep ID:
drep1yffld2866p00cyg3ejjdewtvazgah7jjgk0s9m7m5ytmmdq33v3zh
ダイダロス用👇
drep120m237kstm7pzywv5nwtjm8gj8dl55j9nupwlkapz77mgv7zu7l
二つのIDはダイダロス以外のウォレットではどちらも有効です。ADAホルダーがSIPOにガバナンス権を委任する際に使用できます。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。